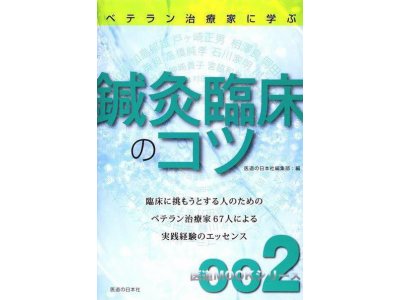こばし鍼灸(掃骨)院 の日記
-
旧98を再掲載.医道MOOKシリーズ002 鍼灸臨床のコツ
2023.12.18
-
医道MOOKシリーズ002 鍼灸臨床のコツ(2008)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【お喋りは問診に通ず】
患者さまも自分も納得できる説明とは?
――インフォームドコンセントーー こばし鍼灸院 小橋正枝
≪広大な領域で、何を選ぶか≫
「医療」という とてつもない巨木の、「東洋医学」という幹の、そのまた 「鍼灸」という領域の、どの枝葉で私は活かされているのだろう。
・触れるか触れないか(鍼が介在すれば、触れなくても鍼と考える向きもある)。
・刺すか刺さないか(九鍼の活用を考えればこれは当然)。
・撫で擦る小児鍼のような皮膚鍼程度から、骨格まで考慮した深部治療まで。
・疲労回復程度から、慢性疾患の徹底治療まで。
・術者の主観を大切にするか、患者の主訴をどこまでも聞き取るか。
・内科的にみるか、外科的に対処するか等々。
・・・選択肢は山ほどある。さて、どれを選ぼうか?
≪私の選択≫
ちなみに私は、運動器を主にした(どちらかと言えばハードな)徹底的にほぐしきる治療法を選んでいる。始めからそれを目論んだ訳ではない。
痛くない、心地よい療法に憧れながら、心ならずも(本当に心ならずも)ハードな治療法を選ばざるを得なかったのだ。
それにはそれなりの経緯があり、そのためには自分を納得させる必要にも迫られた。
自分を説得できたとき、その後に来てくださる患者さまへの説明がたいへん楽になった。
もし、技術的なことに興味をもっていただけるならば、参考に記した「医道の日本誌」をご覧下さい。
≪ある日あるときの、患者さまと私(ばば)の会話≫
わたしは身体を耕すお百姓さん
患者:鍼やお灸って、合う人と合わない人がありますよね?
ばば:好き嫌いは有っても、合わない人はまず居ないと思いますよ。
私たち、お台所仕事をしていて、よく指を切ったり、やけどしたりしますが、治らない人が居る?
その治癒力さえあれば、鍼治療による刺し傷やお灸の火傷くらい治せるのは当たり前。少々の加療反応(メンケン)がでたとしても、生体は必ず元より良い修復をし直してくれる。筋トレの超回復はその原理の1つですよ。
患者:はりって癖になるって聞いたけど?
ばば:お風呂に入ったり、シャワーを浴びたりして清潔にし、血の巡りを良くして心地よくなるのを、癖って言うかなぁ。アルコールや薬物的な常習癖と混同してはいけません。
生体内で、身体が、自力で掃除できなくなったところを、人為的に、じかに洗い流すお手伝いができるのが鍼灸のすごいところですから。
患者:鍼って、ずっと続けないといけませんか?
ばば:例えば、畑。コリコリにこって疲れた皆さんの身体は、踏み固めた地面によく似ています。
私はそこを耕すお百姓さん。一鍬一鍬、耕してあげる。畑でも花壇でも、耕して耕し過ぎることってありませんよね?けれど、いずれその必要がなくなるときが来る。身体も同じ。
それが確認できれば、あとは身体がくれるSOSのサインを見逃さず手当てしてあげる。それが「治未病」です。
≪口腔内に起きることは生体内にも起きる?≫
患者:頚の治療のとき、いろんな音がしますね。
ばば:ずいぶん慣れてきましたね。そう、それはスズメが餌をついばむような、「雀啄術」という方法で鍼を動かすとよく伝わってきますね。ジャリジャリ、ポリポリ、ギシギシ、ニチャニチャ……。
患者:韓国ドラマの「チャングム」みました?
太い鍼をブスッと刺すだけだったけど。あれはどうなんですか?
ばば:みました。当時のハリは1㎜近い太さだったようですよ。とても、今のようなテクニックは使えません。
それに、今は良質で衛生的な鍼が改良されています。
仕事や生活様式も全く違い、ましてや日本人は繊細で、管を使って細い鍼を打つ方法を編み出しました。
患者:へえ。で、私の鍼はどれぐらいの太さですか?
ばば:場所によって違いますが、頚で直径0.2㎜前後、腰やお尻でも0.5㎜径を超えることはあまりありません。
患者:感触も、痛さも、いろいろですね。
ばば:ええ、生体内でも、条件の悪いところでは、虫歯のような骨壊死だって起ているそうです。
患者:身体の中の虫歯?
ばば:そう。実際に多くの方を治療していて、歯科領域で発生しているようなことは、体内でも起きていると感じています。歯周病的な病変も想像できますし、疲れて硬くなった筋肉はギシギシときしむ。疲労物質も長く留まると固形化して歯石みたいにジャリつきます。
鍼に喰い付くようだったり、トランポリンみたいに押し戻して来るような感触がしたり。
ところで、韓国ドラマの「ホジュン」もみましたか?
この人は実在の人物で、主人公のホジュンが科挙の登用試験の中で、口頭試問を受ける場面がありました。
幾つもある鍼法のうち「骨格にまつわる鍼法」について問われ、「骨に至るまで垂直に刺し抜く方法で、骨痺を治します」と答えていました。
私も自分の身体にいろいろ試しますが、虫歯のような傷が付いたところは治療も痛い。
でも、歯石沈着的な部位なら、気持ちは悪いけど「痛った~い」と叫ぶことはありません。
患者:へっ、先生、自分で打つの?
ばば:打ちますよ、手の届く所ならどこでも。
お陰さまで、打つ側の感触と、打たれる側の感覚や気持ちが良くわかるようになりました。
≪圧痛・硬結の殆どは筋の起始・停止・付着部に≫
患者:僕は、トレーニングが好きで、週2回ジムに通い続けています。
血の循りを良くしているつもりなのに、疲れが取れないのはなぜでしょう。
近くの鍼灸院では「週に2回はいらっしゃい」と言われて、できるだけ通ってはいるのですが。
ばば:おそらく優しいタイプの治療でしょう?
ハードなトレーニングを行い、筋力の割にはクーリングダウンが不十分な状態では、深部までの血流改善が果たされていないと思います。
患者:負荷をかけ過ぎということですか?「毛細血管が少し傷付くことで超回復し、その過程で筋力がアップする」と、トレーナーさんから聞いているのですが。
ばば:おお、専門的ですね。
身体を動かすということは、日常動作であれ、筋トレであれ、関節をまたいで植わっている筋肉を、ギューッと縮めることで向こう側の骨を手繰り寄せています。
そこには梃子(てこ)や滑車の原理がフルに活かされています。綱引きでいえば、筋肉がロープで、そのロープの握り手は骨に他ならない。
だから、「どこが」といえば、ロープを握り締める手の平が最も傷つき・錆び付きを繰り返しやすいのです。
私たちが触って硬い(硬結)、圧して痛い(圧痛)ところは、ほとんどが筋の起始部・停止部・付着部(=支点・力点・作用点)なのです。
患者:だから、先生は骨、骨っていうんですか?
ばば:アハハ。もちろん、内科的な見方の達人もたくさんいらっしゃいますよ。
私は自分自身を納得させる必要から、「筋・骨格」からアプローチする方法を選びました。
というのも、体重のおよそ50%が筋肉、同じく20%が骨、締めて70%は身体を支持し動かすための装置、「運動器」です。脳を含め内臓はその中に埋まっています。
従って、運動器を最良に保つことが生体に悪かろう筈がないと考えて、お百姓さんよろしく、皆さんのお身体を耕し続けているのです。
患者:なるほど、日々の草引きや水撒きぐらいは自分でやっておかないといけませんね。
ばば:はい。どうぞよろしくお願い致します。
そして、もう1つお願いしておきたいことは、その大切な「お身体という畑」に撒くお水や肥料は、オーナーである皆さんが召し上がる飲み物・食べ物に他なりません。
口や舌だけに任せず、沈黙している生体にも耳を傾けて、バランスよく、楽しく、召し上がって下さいね。
******************************************************************
医道MOOKシリーズ002 鍼灸臨床のコツ 医道の日本社編集部 添え書き
≪治療者の真摯な態度が患者との信頼関係を作る≫
いかがだったろうか。こうした会話を通じて、治療者と患者は鍼灸について、その治療法について理解を深め合い、合意し合うのだ。
大切なことは、葛藤の果てに自分で納得できる治療法に出合うこともある。(不幸にして、良い師匠に出会えなくても。)
自分で納得していないものを、どうして患者が納得できるように説明できるだろう。どうして、患者が信頼して治療を受けてくれるだろう。
************心 得 帳*********************************************
鍼灸の世界には様々な考え方、治療理論があるが、その中で試行錯誤しつつ自分で納得できるものを選び出し、組み立てなおす必要がある。
自分が納得していなければ、自信をもって患者に説明することはできない。